夏鳥の亡霊と成仏に関する駄文

今年も鳥人間コンテストの放映が終わり、私は三十路の誕生日を迎えてしまいました。
それに合わせた駄文です。思い出話みたいなものなので、読むも読まないも、写真だけ眺めていくのも自由です。
今大会はBirdman House 伊賀(以下BHI)のサポートメンバーとして、それに大阪公立大学 堺・風車の会(以下風車の会)のOBとして行ってました。

 上:大阪公立大学 堺・風車の会「willow」
上:大阪公立大学 堺・風車の会「willow」
下:Birdman House 伊賀「Phantom」
両チームの結果は放映のとおりです。風車の会は主翼は飛行中に破損してしまって1100mちょっと。BHIは70kmゴールライン手前で着水。正確な距離は公式サイトで見てくださいな。全チームの記録は下の方にある「大会の歴史」から「第45回大会」で見れます。
後者について、人力飛行機の世界記録フライトのダイダロス88が、砂浜を直前に着水した瞬間と同じじゃねえか、なんて思っていました。
去年、現在の所属チームであるチームあざみ野で大会新記録を出して成仏したと思っていたのですが、今年やっとその実感できた気がするので、徒然と筆を執った次第です。
亡霊になった瞬間の心当たりからでも記しましょうかね。
朝ドラ『舞いあがれ!』完結に寄せて
連続テレビ小説『舞いあがれ!』ついに終わりましたね。
本作品で私はなにわバードマン編に「大阪公立大学 堺・風車の会」のOBということでここの一員として、更には資料提供として本編のクレジットに名前が載りました。
実は提供した資料の一部は劇中ポスターで使って頂きました。1枚目は実際に60kmの大会記録を持つBirdman House 伊賀さんの1号機。テストフライトの時お手伝いで撮影したもの。2枚目は2018年風車の会の記録飛行で撮影隊員が撮ったものです。 #舞いあがれ #人力飛行機考証 #舞いあがれ美術図鑑 https://t.co/MfuK6NrapX pic.twitter.com/5CmWj9X3Hb
— 雪夜彗星 (@sncomet) 2022年10月28日
最後まで通して見て「よくここまでやってくれた!」というところも「どうしてこうなったんだ」というところもありましたが、総じて熱い展開の物語だったと思っています。せっかくなのでちょっとした関係者として、あるいは口煩い一般飛行機野郎として思ったことをつらつら書き記して行こうと考えた次第です。
なにわバードマン編以外のパートについては一切関わっておらず脚本も渡されていなかったので一般視聴者と同じ視点になります。
今まで朝ドラは仕事に行く前や、Twitterのトレンドで少しばかり見る程度に追いかけたのですが、今回ばかりはTwitter上の反応や色んなインターネット記事を読み漁っていました。
■なにわバードマン編
本当はなにわバードマン編の放映が終わったあたりに何か書こうと思っていたのですが、後輩にチームブログでの記事依頼があったので最終回まで待つことにしていました。
私は航空学校に行っていないのでどこまで現実味がある描写だったのか分かりませんが、なにわバードマン編に関していえば本当に実際の人力飛行機関係者の雰囲気がよく出ていました。正直、ここまで描いてくれるか、というぐらいの再現度でした。
一週目の「リブ破損」「書類落選」「テストフライトクラッシュ」というコンボは完全に狙いに来ていると思われても仕方がないぐらい、観てて胸が痛む展開でしたね。人力飛行機やってて辛い出来事詰め合わせセットですよ、本当に(褒めています)。
読み合わせや撮影の現場等にも立ち会い、作業やテストフライトの演技について教えたのですが、元の脚本が良かったのも大きかったでしょう。ここは脚本家の力もさることながらインターステラテクノロジズ代表で東京工業大学MeisterのOBの稲川さんの考証のおかげだと思っています。そこに拙作の映画『俺ら、夏鳥』の影響もあると嬉しいなあ。ちなみにこの作品はこちらからDVD販売中ですので興味がありましたらぜひ買って頂けると嬉しいです。
なにわバードマン編の最大の見せ場、琵琶湖岸での記録飛行は本当に色々と拘って作り込んで頂きました。鳥仲間に本作を勧める時は大体「飛行宣言板やTバーまで作ってもらえた」と言えばウケて興味を持ってもらえています。
#舞いあがれ ついに始まりました記録飛行。コンテストと違って自分たちで場所の利用申請やボート、救助ダイバー、公式立会人、ライセンスなどを手配しないといけませんし決まりも色々あります。全部というわけでもないですが、劇中でも「記録飛行に必要なもの」が再現されています。 #人力飛行機考証
— 雪夜彗星 (@sncomet) 2022年11月8日
かと言って全部が全部、現実的なものでもなくて「劇中のような状況での飛行からの骨折」も考えづらい話ですし、何より記録飛行前日にたこ焼きパーティは出来ないですね。部員は準備に追われて心身ともに疲れてそんな時間と元気はありません。
ちなみに2018年の記録飛行の時は私は既にOBだったにも関わらず銭湯のお休み処で仮眠して閉店に合わせて撮影隊の面々とともに彦根港に行きました。
余談ですが、舞いあがれ世界では大会で未練を残していつまでもOBチーム等で関わっているような人たちのことを「イカロスの亡霊」なんて言われていそうですね。実際に「琵琶湖の亡霊」となってしまう人がいますから。
大会じゃなくても綺麗に飛んで終われたら本当に幸せな方だよな。実際は無慈悲に夢が潰えて、琵琶湖に魂を囚われた亡霊になる人達が毎年いるわけで。#舞いあがれ
— so1ro (@533so1ro) 2022年11月9日
目標達成を出来なかったとしても部員たちが満たされる(未練を残さない)展開で本当に良かったです。
一年生で成仏できる鳥人生、歩んでみたかったですね……。
■空飛ぶクルマ
製作当初からあらすじに「五島列島の島々を結ぶ小型電動飛行機を飛ばす事」とあったので俗に言う「空飛ぶクルマ」が出てくるかと思っていたのですが、こんな形で出てくるとは思ってもいませんでした。
刈谷先輩を始めなにわバードマン編の登場人物が再結集して飛行機を作る、といえば確かに「熱い展開」ではあるもののあれだけ人力飛行機の設計に入れ込んでいた人が有人マルチコプターを作るのか、というのはあまり現実にはない展開かと。鳥人間OBは有人マルチコプターに関して否定的な連中が多いので。
ただ一般には人力飛行機を作っているから空飛ぶクルマ(有人マルチコプター)を作る、自然な流れと考えてしまうのは止むを得ない事だと思いますが……。主人公がIWAKURAで作るとか全く新しい人たちと作るものかと思っていたので、ここまでなにわバードマンのOBたちががっつり関わる展開がわかっていれば私も一言、監修の時言えたのになあ、なんていう後悔もあります。
でも最後に登場した「かささぎ」は有翼のティルトローター機でちょっとホッとしました。ツッコミどころは内装はじめとして色々あるのですが、最後まで有人マルチコプターにならなかったのでまあよしとしましょうや。
ただ「それから、六年」という貴司君のナレーションで省かれてしまった間こそがえeVTOL「かささぎ」開発のドラマがあったかと思うので飛行機野郎としては気になるところです。ティルト機構の開発やら各種証明の取得やら……。ここは今までの伏線を最後にまとめて回収するためにこうしたのかな、とも思っていますが。
でも間違いなくISO規格(航空機用ネジの話で)や型式証明という単語が出てきただけでも評価に値することでしょう。正直、一般視聴者層からすれば「なんだそれ」という感じで出さずに物語を進める事もできるわけですから。
日本のeVTOL(電動垂直離着陸機)ベンチャー2社やJAXAも撮影協力に入っていたにもかかわらずこの形か、という話も見ましたがどの程度監修に入ってたのか分からないので考証サイドをあまり責めないほうが良いかと。予算の都合もあるでしょうし、伝えても演出やその他事情で受け入れられない事もありますから。
人力飛行機に関してはちゃんとしていた、と言われるとそれは多分、製作サイドがあまりにも情報がなくこちらから本当にあれこれ伝えていたので、それが効いていたのだと思っています。
■物語を通して
細かいところは他にもあるのですが、個人的にいちばん気になるのは舞の高校時代、何をしていたか、なんですよね。あれだけ飛行機が好きならイカロスコンテストや浪速大学に人力飛行機チームがある事を知っている気もするんですが知らない風でしたし……。あのバート・ルータン氏までを知っている人が、という違和感があります。
ただイカロスコンテストはもしかしたら劇中世界では深夜放送などでそこまでメジャーではないのかもしれませんが。
飛行機を作っているやつはどうしてこうも面倒なんだと思うかもしれませんが、それぐらいの人でないと飛行機を作らないのだと思っています。
「舞ちゃんは旅客機のパイロットになってほしかった」や「刈谷先輩は旅客機を作る方にいくものと思っていた」という感想をTwitterで見かけましたが、そんな人に送りたい投稿がこちら。人力飛行機のOBチーム、CoolThrustの代表の方のツイート。
#舞いあがれ は人力飛行機編やパイロット編から町工場編になって何が描きたいか分からん、という意見もある。けど自分には紛れもなく、空にあこがれた日本の若者の物語だと思う。それも残酷なくらいリアルな。その残酷さが悲壮感なく描かれているところが、おそらく卓抜なのだと思う。
— ykuni (@hpap_ykuni) 2023年3月16日
こんな風に取り上げられるOBチームもありますけれど(実際は学生OBで結成されてたまたま何人かが航空系に行った)も、そんなに航空系ばかりにみんな行けるわけでもありませんし、人力飛行機やっていて航空業界やっている会社に入ったとしてもその部署に配属されるとも限りません。劇中だと刈谷はアビキル立ち上げる前には自動車メーカーに行っていましたが、風車の会OBも自動車メーカーに行く人が多いです。
■最後に:『舞いあがれ!』で空へ憧れた人たちへ
ここまで色々と書きましたが『舞いあがれ!』を見て飛行機を作ること、飛ばすことに興味を持ってくれる人が増えたら飛行機チームのメンバーとして、そしてドラマ協力の一人として嬉しいことはありません。
かと言っても「どうやって始めたらいいんだ」という方に向けて空への憧れに取っ掛かりになりそうな事を書いてこの記事を締めたいと思います。誰が読むのか知りませんけど。
鳥人間コンテスト、あるいは人力飛行機に対しては飛行機界隈から賛否色んな意見がありますが、それでも色々な大学にチームがあり、日本では空への入り口としては敷居が低い方ではないかと思っています。
ドラマに協力した人力飛行機チーム、堺・風車の会も新歓シーズンを迎えて部員募集中です。劇中以上に汗と涙でまみれるドラマチックな日々が待っています。「自分の通う大学にはチームがない」という方も風車の会は他の大学の人も受け入れているので近くに住んでいる人で興味があればぜひ連絡を取ってみてください。
ちなみに最初からパイロットやりたい、と思っているならグライダーを飛ばす航空部があればそちらがおすすめです。鳥人間コンテストは「作る方」で全員が飛べるわけでも無いですから。あ、そっち行っても鳥人間コンテストの飛行機を本物じゃない、みたいにいうのはやめてください。鉄骨丸出しコックピットに座らせるぞ。
「昔はやってみたいと思っていたこともあったけれども、もう社会人になってしまったしなあ」という人にもグライダークラブやウルトラライトプレーンという選択肢もあります。空を飛ぶ気持ちよさならパラグライダーやハンググライダーの体験から始めるのも良いでしょう。宇宙関係なら人工衛星を趣味で作っている団体「リーマンサット」なんてどうでしょう。
それにものづくり方面なら飛行機保存にかかわるというのもありです。こちらは航空系の博物館に行ってみるとボランティアを募集しているかもしれません。ちなみに航空機の保存に関しては以下の書籍は本当におすすめです。
» 航空機を後世に遺す歴史に刻まれた国産機を展示する博物館づくり|グランプリ出版
どこに行くにせよ、まずは見学を始めて自分に合うかどうかみてみるのが良いでしょう。歓迎して色々と話して、見せてくれると思います。
空への憧れの、実現の仕方は人それぞれですし、人や運の巡り合せもあるでしょう。『舞いあがれ!』でも途中で飛行機部品への話がありました。
どこでどうなるかなんて分かりませんから、まずは自分の「やってみたい」に従って動いてみれば、多少回り道でも憧れはどこかで、何かしらの形になるかもしれません。
私も芸術大学に通って、興味があるからと風車の会に連絡を取ってみてここまでつながってきた訳ですから。
当初思っていた形とは多少違っても、何かしらの形で続けていれば思わぬ事がおきますよ。
でかい花火がいくつも上がった年の暮れに
独り言の回です。
2022年が終わります。個人的にはでかい花火が何発も打ち上がったような1年でした。
#2022年自分が選ぶ今年の4枚
— 雪夜彗星 (@sncomet) 2022年12月31日
仕事を辞め、フリーランスで活動し始め、朝ドラ『舞いあがれ!』協力、鳥人間コンテスト新記録優勝、国際鉄道模型コンベンションへの出展参加、初の自分のライブスチームの運転などこれでもかというぐらい詰め込まれた1年でした。来年は落ち着きたい…… pic.twitter.com/z8flT210AB
「人生のどこかで人力飛行機が登場する商業作品に関わる」「30代には全国配給の作品のクレジットに名前を載せる」という人生の目標を叶えてしまい、更には鳥人間コンテストでチームが大会新記録を出して優勝までしてしまいました。
それに早くても40代だろうと思っていた5インチゲージのライブスチームを2020年に購入していましたが、それの初走行、そしてこれも「そのうち」と思っていた国際鉄道模型コンベンションにも桜崎鉄道さんのお誘いもあり出展することができました。
こんなに詰め込まれることがあるのか、というぐらいで寿命が縮んでいないか疑っています。
頑張ってもうまくいかないことは多いですし、私もその例に漏れず喜びなんて刹那的ものです。なので今年の怒涛っぷりは運が良かった、と言われたらその通りですけれども、高校時代からつながって来るものはあるなあと思っています。
端的に行ってしまえば、高校時代、しがない文系男子だった映画を作るようになり、芸大に進み、学外の人力飛行機チームに入り、卒業後に自主で人力飛行機の映画『俺ら、夏鳥』を作り上げ……と。冒頭で書いた目標もこれらの過程の中で出てきたものなので当初からの夢、というには少し違いますが、
来年はどんな事があるでしょうか。正直、今年これだけの事があったので落ち着きたいところですが、映像も、鳥人間コンテストも、ライブスチームも目指していたところに到達してしまったので、何か新しい目標、せめて新しい歩く方向ぐらいは決めたいですね。30歳にもなりますから。
実際、春頃にはちょっと今までは違った感じのお知らせも出るかもしれません。
それでは、皆様、良いお年をお迎えください。来年も雪夜彗星をどうぞよろしくお願いします。
2018記録飛行撮影とフィルムの話
本記事は以下の企画の参加記事です。
人力飛行機・鳥人間コンテスト Advent Calendar 2022 - Adventar
というか、このブログ、1年以上更新してなかったんですね。まあてんてこ舞いな1年を過ごしていたので書きくさして中途半端なところで停まった下書きが沢山ありました。いつか日の目を見るのでしょうか……。
私らしい話ということで記録飛行の撮影に関するお話です。
──え! 資料提供したドラマの話期待した!? メイキングの話を公にするのはここでもないし多分俺でもない。どこまで公にできる話題かどうかもわからんしそれは実際に会ってきいてくれ!
2018年の大阪府立大学 堺・風車の会の記録飛行の撮影時の書くことにします。まずは以下の動画をご覧頂ければ。噂の飛行機朝ドラ『舞いあがれ!』でも同じようなシーンがありましたね。
機体にかぎらず人の動きもここまで映っており、公開している記録飛行も珍しいと思うので撮影隊取り仕切りとして色々思い出しながら書いていきます。特にフィルムについては危惧している事もありますので後半に徒然と思っている事を。
■機材構成
今回、フライト予定日が複数日あったので日によって出てきた機材は異なるのですが、記録に残っている機材だとで以下の通り。
Canon EOS 5D mark III / 50D / Panasonic LUMIX GH5s / GH2 / OLYMPUS E-M1 / PENTAX K-70 / NIKON D5500 / P900 / FUJIFILM X-T2 /他
MINOLTA α-Sweet / α7000 / 他一台(多分EOS系だったかと)
・ドローン
DJI Phantom 4 Pro / DJI Mavic Air
動画についてはビデオカメラの類は1台もなくGH5sなど動画スチルカメラで撮影していました。
■機材配置
基本的には彦根港だけに配置し、ボートには写真用のデジタル1台、フィルム2台だったかと思います。ボランティアで組織した事もあって水がかかるなどによって故障など起きても補償がどこまでできるか難しいところだったので最小限にしました。
2機のドローンは機体後方と斜め前方向で待機し、両者高度違えて飛行するようにしていました。
ドローンもボートからの離艦を考えたのですが、難易度が高い事、それにドローンの離着艦のためにボートを停めたり動かさないといけない事もありこちらも彦根港から制御できる範囲で飛ばす事にしました。
■フィルム機材の手配
今回の記事でいちばん書きたかった話がこちら。FAIの記録飛行挑戦時にマストとなるフィルム撮影について。
ご存じの方もいるかと思いますが、記録飛行宣言板やライセンスを持ったパイロットと公式立会人、離陸や2mの高度通過、スタートやゴール、着陸(着水)の様子を「フィルムカメラ」で撮影する必要があります。
かつては「デジタルかフィルムか」なんて議論があったこの業界もデジタル一辺倒でフィルムはごく一部の領域としてほそぼそとかろうじて生き長らえている状態で、なかなか実務で用意しようとすると難儀なものです。
この記録飛行の際には1台は私が持っていたフィルム一眼レフ、MINOLTA α7000に加えて、家の近くで見つけたα-sweetを買い足しました。マニュアル露出のフィルム機は複数台持っているのですが、流石に露出ミスが許されず、他の人に託すとなるとこの手のカメラは心配なので……。ちなみにレンズも含めて手配して5,000円しなかったと思います。α系の中古は割と安い値段で出ている印象ですね。
それに中に装填するフィルムも入れないといけません。3台用意したカメラのうち、ISO400とISO800を入れていた覚えがあります。台数は忘れてしまいましたが……。
2018年当時はまだ富士フィルムがまだいくつかの種類のフィルムがあり、感度も選べたのですが、今となってはこの状態。2018年当時はまだISO800のフィルムもフジから売っていたのですけれども、無くなってしまいました。今は下記に紹介するKodakのものが主流であとは趣味性の高いものぐらいです。
あと現像も昔だとスピードプリントといって1日もあれば現像してくれる写真屋さんはいくつもありましたが今となってはラボに送るので数日かかるのは当たり前、みたいな感じとなってしまいました。
フィルムを取り巻く環境は趣味の分野としてみても年々厳しくなっているので、ときとともに手配は難しくなると思っています。
■フィルムに対する個人的な意見
私はフィルムだからといってそこに真実性が宿るわけではないと思っています。スターウォーズもインターステラーもポスプロでエフェクトがかかっているとはいえ、撮影はフィルムでやっていますから……。
それに今時、スタジオでは高精細LEDパネルや大きなスクリーンに映像を投影して背景として利用する事も増えています。そういうところに映し出されたものをフィルムで撮る事も現実的に可能です。ドラマ『舞いあがれ!』でもばんばの軒先から見える五島の景色はLEDパネルで出しているそうですよ。
写真としての信憑性ならむしろRAWで撮影したデータや詳細に撮影情報が残るExifのほうがまだ信用に足るのでははないかとさえ思っています。最近はGPS内蔵で位置情報をカメラに残せるものもありますし。
公式立会人による時計等確認もあるので、そこで記録撮影に利用するカメラの時計設定とGPSログの確認をして、みたいなのが良いのかなと思っています。
プロを雇えば良いですが、学生のクラブや好きで集まっている人たちが大半である人力飛行機チームにおいてそう簡単にプロに頼むのも(だから雪夜彗星に頼
学生だと大学にある写真部に相談するのも手かもしれません。フィルムを使っている人がどの程度いるのかは部によるので本当に声を掛ける場合は確認しましょう。
■そんな事はいっても今はフィルムで撮らないといけない
ここで話が終わっては無責任なので新品で比較的入手しやすいカメラやフィルムを紹介しておきます。ただこれも2022年12月でのお話なのでいつどうなるかはわかりません。
・カメラ:Kodak EKTAR H35
名門フィルムメーカーのコダック社が2022年に発売した最近出したコンパクトフィルムカメラです。日本語の公式サイトが見つからなかったので海外のURLを引っ張ってきました。ハーフカメラというもので通常のフィルムの一コマを縦2つに割る事で指定のフィルム枚数の2倍撮れるようになります。36枚フィルムを入れると72枚撮れます。その分画質は落ちますが、よほど大きく印刷しない限りは問題ないでしょう。
写りについてはまあ甘く、絞りもF9.5、シャッタースピード1/100で固定というトイカメラ感も否めないですが、公式立会人の方いわく、小さくてもとりあえず映っていれば良い」という事なので、目を瞑って飛んでいる飛行機の方にレンズを向けて撮っておきましょう。レンズは22mmとありますが、ハーフフレームなので35mmフルフレーム換算だと44mm相当でしょう。個人的に好みの画角ですが、専用テレコンなんてあると良いですけどね。
おすすめしておいてなんですが、私はハーフカメラ、FUJICA Halfというものしか持っておらず、映りについては知人の方に紹介頂いたこちらのツイートなどが参考になるかと思います。
それに新たに発売されたハーフカメラということで話題担ったこともあり「Kodak H35」と検索するといろんな方の記事が出て来ますので、気になった方は調べてみてください。
あと新品のフィルムとなるとかすかな希望の光はリコーペンタックスが新しいフィルムカメラを作る、というリリースがつい先日出たことでしょうか。ただ、記録飛行撮影に向いているカメラなのか、金額も手が届きやすいのか、使いやすいのか(オート露出で撮れるのか)などは不明です。
ただ上記のH35がだめならやっぱりオートで撮れる中古のフィルムカメラを探してくるのは無難なんだろうなと思います。
・フィルム:ISO400編「フジカラー SUPERIA PREMIUM 400」
2022年12月現在での入手性、現像の対応店の多さ、感度のバランスを考えるとこのフィルムが「記録飛行に限って言えば」扱いやすいのではないかと思います。ISO400という感度も通常の撮影では高めと思われそうですが上記のH35カメラと組み合わせるとなるとF9.5という暗さや暗いうちから撮らないといけない事を踏まえると最低でもこの値はほしいところです。
・フィルム:ISO800編「Kodak PORTRA 800」
こちらのフィルム、Kodakの公式サイトが見つからなかったので検索してトップに出てきたマップカメラのサイトを紹介しておきます。
もう夜間撮影専門みたいな感度ですが、それでもF9.5、1/100のカメラで使うとなるとこちらのフィルムも選択肢に入ってくると思います。
フジのものに比べると暗いところがよく映る分、ノイズが多くなりますが、記録飛行はとりあえず写っていれば大丈夫なので……。あとはKodakは現像に時間がかかるお店が多いのも注意しておいたほうがいいところですね。
とまあ、徒然と記録飛行撮影について2018年の事を思い出しながら書きたいことを書き出しました。何かもっと詳しい話を知りたい方がいれば私のTwitterの方からお気軽にご連絡下さいね。
ただでさえ申請やライセンスが大変な記録飛行挑戦、記録のカメラの事で話を進められない、なんて事が起きないようになるのが一番良いと願っています。
いずれは「フィルムによる記録をいつまで信じるのか」みたいな話をスカイスポーツシンポジウムでしたいなとも考えていますが、果たして叶うのやら。
追伸:例のドラマの記録飛行シーン、公式立会人に挟まれている舞ちゃんの絵がないか期待したんですが、なかったですね。
自主製作映画のお手伝いに行く時、何を持っていけば良い?
かれこれ、10年以上自主製作映画を作っているのですが、スタッフの人手が足りず、興味を示した全く映画の現場を知らない人にお手伝いをお願いすることも多くあります。私が現場で、監督、撮影プラスαで色々兼任してワンマンオペレーションでやろうとしているのも要因なのですが。
来て頂いた方には、マイク・照明持ちだとか、荷物番だとかをお願いしてますが「何か持っていったほうが良いものある?」と訊かれる事もあるので記事にする事にしました。

ただ、あくまで私の周囲での話なので、もっと別のものがあるとありがたいという人もいるでしょう。話半分で読んでいって下さいな。
何もここに書いてある全部を持っているからと言って無理して持っていく必要もないと思う。持って行きやすいものだけもっていけば大丈夫ですよ。
-
テープ類 お役立ち頻度:★★★★★
テープと言っても色々ありますが、一般の家庭にありそうなものだとまず養生テープ。剥がしやすい緑色のものがメジャーですね。バミリなどの印をつける時等に使います。ガムテープも何かの応急処置等でも使いますね。
マスキングテープを持っていればこちらも持っていくと良いかもしれません。
撮影現場の人だと「パーマセルテープ」という剥がしやすい特殊で効果なテープ(1つ1000円前後)を身につけている事も多いですね。ただちょっとお手伝いの人がわざわざ買って持っていく必要はないと思います。
- 乾電池型充電池 お役立ち頻度:★★★★★
いわゆるエネループみたいなもの。みんな持っていっても現場にあってもなんだかんだ充電が切れてしまいます。
多く、電池を買いにコンビニ等に走る事態になる事も多々あるのでもし持っている人がいれば「自分のものと分かるようにして」回収を忘れないようにして貸してあげると喜ぶ人がいると思います。 - 油性ペン お役立ち頻度:★★★★★
上記のテープへのメモ書きや下に書く紙コップで人を区別する時等で何かと使います。ボールペンだと細いので視認性が良くないので……。
ちなみにバッグを荷物置き場に置きっ放しにすることも現場ではよくあるのでペンやテープ、電池は持ち歩くようバッグに入れておいた方が良いです。 - 紙コップ お役立ち頻度:★★★★★
人が集まる時には2Lペットボトルを紙コップに小分けして飲むというのは定番ですが、撮影の現場でもそれは同じです。
あとお手伝いでやる事ないな、という時になればコップに入れてスタッフやキャストに配ってあげるのも吉です。中には集中して水分補給を忘れている人もいたりしますから。 - クーラーボックス・保冷剤 お役立ち頻度:★★★★☆
夏にあると救われます。別にプラスチックハードケースのものでなくても、折り畳める布製のバッグでも保冷できるものでも十分すぎます。野外での撮影である程度冷たいままで飲みものがあるだけで幸せになれます。本当に。 - 虫除けスプレー お役立ち頻度:★★★★☆
夏場の野外での撮影の際には本当に必要なのですが、何かと持ってくる人が少なく、現場で買いに行く事が電池同様に多いものです。
なお10月の現場で虫除けスプレーを持っていかなかった事を後悔したので真冬以外はあって損はないと思います。 - 無線 お役立ち頻度:★★★☆☆
一般の家庭に無いものかもしれませんが、他の趣味(サバゲーとか人力飛行機とか)のために持っている人もいるだろうということで選びました。特に複数式持っていれば最低2式は持っていくと助かる場面も多いと思われます。私が無線を持っていった現場は必ず使いました。
交通整理する時、部屋の外から合図を送る時等。なければスマホで電話する事も多いですが、それよりは無線の方が勝手が良い場面も多いです。
ただ、慣れてない人が使うと思わぬトラブルが起きる事もありますので誰かに持たせる時は使い方を教えてあげましょう。あとチャンネルの設定も忘れずに。 - レンズ、マウントアダプター お役立ち頻度:★★☆☆☆
もし、写真は撮るという方ならメイキングを撮るためにカメラを持っていくかもしれませんが、余力があればレンズも少し持っていくと役立つかもしれません。
仮に現場で使うカメラとマウントがが違っていてもアダプターがある事もありますし、夜間や暗い屋内での撮影となる可能性が広角レンズや明るい大口径レンズがあればその場で「貸して!」となる事もあります。 - 工具類 お役立ち頻度:★★☆☆☆
使わないだろうけれども、車で行くし載せておくか、となんとなく電動ドリル持っていったら本当に美術の方に貸した事がありました。 - 飲食料 喜ばれる度:★★★★★
差し入れといえば食べ物、飲み物、というのは鉄板ですが、冷蔵/冷凍庫で保管しないといけないもの、すぐに食べないといけないもの等は避けてほしいところです。みんなすぐに食べられるわけではないので。屋内の現場で、冷蔵庫があれば良いのですが……。
具体的には小さめのパンや小分けのお菓子など軽くつまめるようなものが良いですね。
ざっと思いつく限りのものを羅列してみました。
普通は通常スタッフ等で用意しておくべきものばかりでは有るのですが、そこは自主製作映画です。頼れるものや力は使います(笑)。
基本的に私が誰かに手伝ってもらうのリストも兼ねているのですが、もし、何か他にあればよいものがあればコメント欄に書いておいて頂けるとこの記事を見た人に役立つかもしれません。
LUMIX AWORD 2020入賞作品「祈りを捧ぐ」制作レポート
完全に時期を逃した感もありますが、書きかけた記事があったので今更ながら放出します。「LUMIX AWORD 2020」に出品し、優秀賞を頂いた作品「祈りを捧ぐ」の制作レポートです。
こういうのを書いておけば「どうやって映像編集してるの?」という時に「これを読んで」とも案内できますし。
受賞URL: https://lumixclub.panasonic.net/smart/contest/award_20/result/
作品視聴先: Lumix Club / YouTube (以下) / Vimeo
【主な使用機材,ソフトウェア等】
・Panasonic GH5S
・Ronin-SかRonin-SC(借り物だったのでどちらか)
・Phantom 4 Pro
・DaVinci Resolve
今回は別件で撮影依頼のあった素材を利用しているので今回のエントリーに合わせて再撮影、というのはしませんでした。なお、元の映像は以下になります。ずらずらとプレビューが並びます。
今回、作品の尺が30秒以内という事だったのでまずその長さの中でいい感じに使える音楽を探すところから始めました。神社が被写体なので和風の音楽にする事は決めていたので、その中であれこれネット上を物色。本当なら仲の良い作曲家の方に「こういう音楽を作って!」と依頼できるといいのですが。
今回は「おとわび」というサイトで公開されていた「いにしえより続く街、太宰府」という曲をお借りしています。作曲者はふみこみどり様。ありがとうございます。
さて、音楽は見つかりました。尺に合わせて音楽を切り出し、その後、撮ってあるショットの中から個人的に印象深い箇所を抜き出してとりあえずタイムラインに置いておきます。大体絵の方の尺が延びてしまうので、見せたい絵を絞りつつ音楽のキリのいい所でカットしていきます。
ただ全てを音楽のリズムに合わせてしまうと音楽に映像が負けてしまうと思っているので、映像として見せたいカットの尺と音楽に合わせて映像を切るバランスを意識して編集してます。
あとここで応募するコンペの狙いにも合わせて編集します。シンプルにかっこいいカットを音楽に合わせて並べるだけで良いのか、あるいは何かしら流れを組み立ていくのか、が変わっていきます。今回のLumix Award2020の動画については「自分が伝えたいテーマを物語にして」とあったのでそれに合わせています。ただそれについてはここで言うのは野暮でしょう。
実は今回一番悩んだのが題名。友人や神社の宮司さんにもご相談して公開したものに落ち着きました。ここも上記のコンペに合わせて変えるところでもあります。
他にも「奉祀」「榊の枝に添える祈り」というタイトルも候補にあったのですが、宮司さんからは「宗教色が濃いのを嫌い人もいるから」との事で候補から外すことに。難しいですね。
もちろん総合最優秀賞を狙ってはいましたが、結果は冒頭の通り。次回もいい作品を作れる題材があれば、エントリーしたいところではありますが、そういったものに出会えるでしょうか。
ではでは。
機関車工作にBlenderを使った話



■設計



■板材切り出し図面の作成




■ディテールアップパーツの作成




・軸受け(ピローブロック隠し)



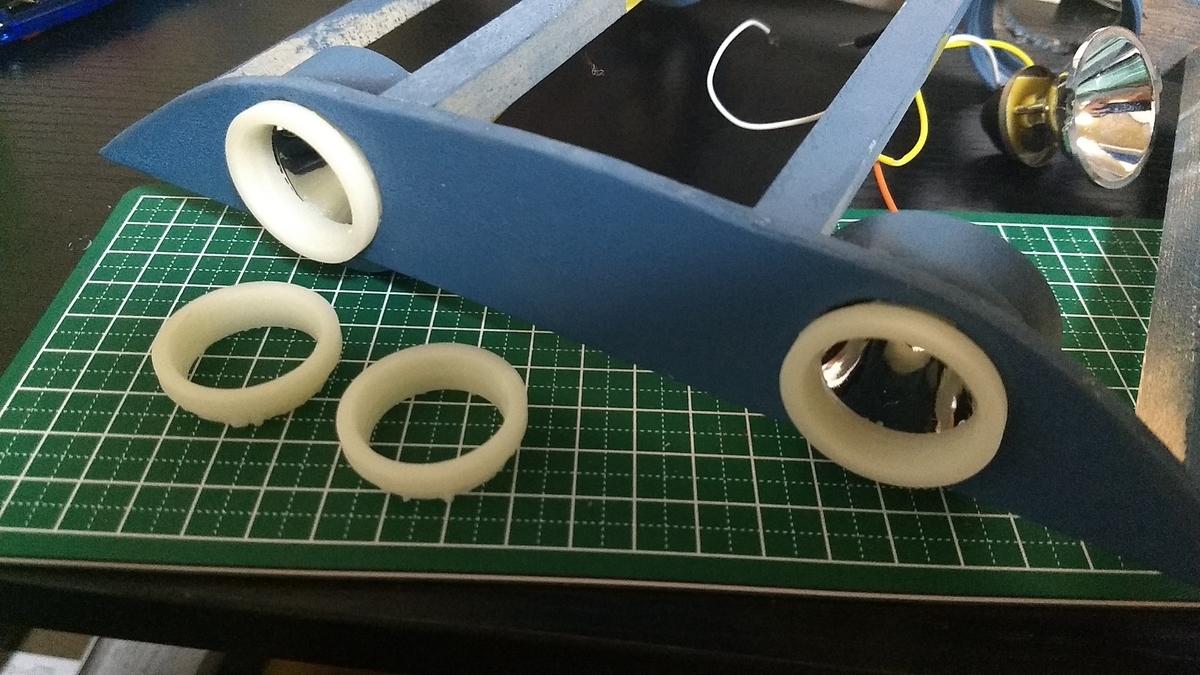
使用レジンはいずれもSKレジン様の水洗いレジンです。

Blender関係無いですが、石炭を燃やして本当に蒸気で動くフォルテの工作の状況がこちら。模型エンジンで有名な小川精機製のキット。8月からずっと作っています。(注:家です)
